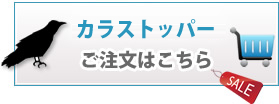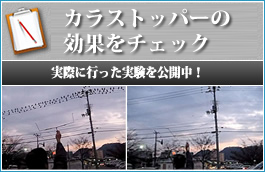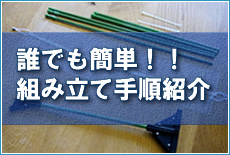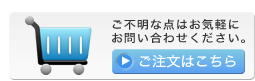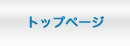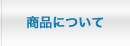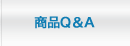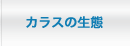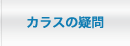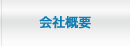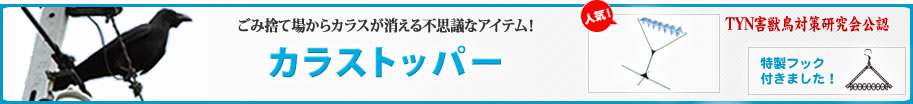役に立っているカラス
カラスはゴミを散らかす、大事に育てた果実を食べてしまうなどといったいわゆる害も及ぼしますが害だけではなく役に立っていることもあります。
まず一つは、道端でネコなどが車に轢かれて死体になっているのを目にすることがありますがそれを食べてくれます。
一見、気持ち悪い光景ではありますが、もしカラスが食べてくれなければ誰かが片付けなければならなくその死体を処理しなければなりません。
一番簡単なのは、土に埋めることですが特に都会にはその土が少なく埋めれるところも早々ないのが現状です。
保健所に連絡して処理してもらうにも誰かが連絡しなくてはならず多少なりとも面倒ではあります。
ということは、カラスはサバンナのハゲワシのようにスカベンジャー、掃除屋の役割をしているといえるのではないでしょうか。
ハゲワシはサバンバの死体を食べることで自然界をキレイにしています。カラスもある面では同様の働きをしています。
他にも、巣の提供という役割をカラスは担っています。
鳥の中には、カラスやツバメのように自分たちで巣を作る習性がない鳥がいます。
日本では、ハヤブサの仲間のチゴハヤブサやフクロウの仲間のトラフズクなどがそれにあたるそうです。
それらの鳥が特に利用するのがカラスの巣だそうです。
またもう一つ、先日記事にしたカラスが食べるウルシ属の実ですがカラスはこれの種子散布の役にも立っています。
カラスが食べることによって種子が運ばれ分布を拡大することができるそうです。
ウルシ属の種子はそのまま蒔いてもすぐには芽が出ずに発芽まで2~3年は時間がかかるそうですがカラスが食べることで種子の皮がむけ発芽率が上がるそうです。
というわけで、ウルシの仲間にとっては、カラスはいなくては困る存在のようです。
また、ウルシは日本の代表文化である漆塗りの器や和ロウソクに使われますので結果的に私たちの生活にも役に立っているといえそうです。
自然界に無駄なものなど何もないのだなとあらためて感じさせられます。
参考図書:カラスの常識(著:柴田佳秀)
カラスの生態カテゴリー 関連記事(10件)
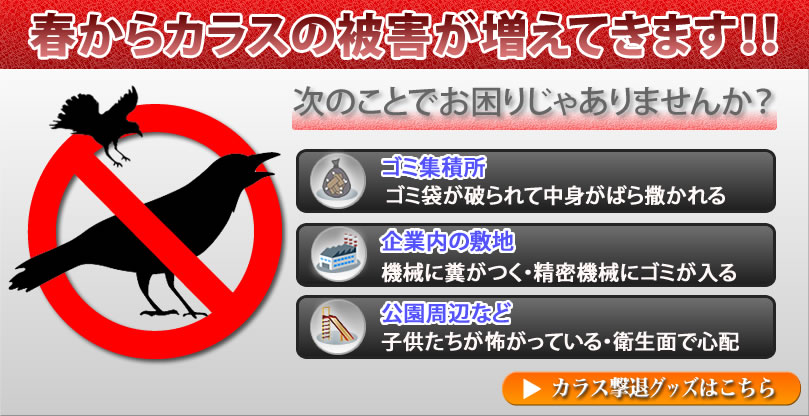
←「変なものを食べるカラス」前の記事へ
次の記事へ「カラスなぜ逃げるの効果的な使い方」→